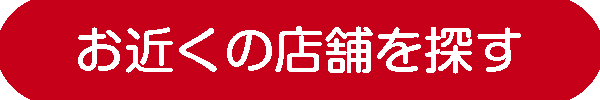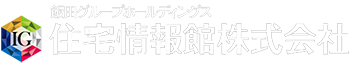9月17日、令和6(2024)年の基準地価が発表されました。コロナ明けから上昇が続いていた地価は、全国平均で+1.4%と3年連続の上昇となり上昇幅が拡大しました。今回は東海・関西エリアの地価上昇率が高い沿線・駅について解説します。
目次
1. 全国平均(全用途)は住宅地・商業地とも3年連続の上昇
2024年基準地価の変動率は、全国平均(全用途)で前年の1.0%から1.4%へと上昇幅を拡大し、3年連続の上昇となりました。用途別に見ても、住宅地(0.7% → 0.9%)、商業地(1.5% → 2.4%)とも上昇が加速しており、地価が力強く回復していることが確認できます。
要因としては、低金利政策の継続、住宅取得支援施策などにより、都市部を中心に住宅需要が引き続き旺盛であること、また商業地も主要都市で店舗・ホテルなどの需要が高く、オフィスについても賃料が上昇していることなどが挙げられます。また、観光客やインバウンドが回復した観光地で上昇率が高くなった地点もみられます。
1-1. そもそも基準地価とは
基準地価とは、国土利用計画法に基づき、全国2万ヶ所以上の基準値の1㎡あたりの価格を、各都道府県知事が公表するもので、毎年7月1日時点の地価を9月に発表しています。1月1日時点の地価を公表する「公示地価」と同様、適正な地価形成を目的とし、土地取引の指標となる価格として活用されています。
1-2.三大都市圏は上昇幅を拡大。地方四市は上昇幅が縮小
次に圏域別に直近1年間の地価動向を見てみましょう。
■2024年基準地価の変動率
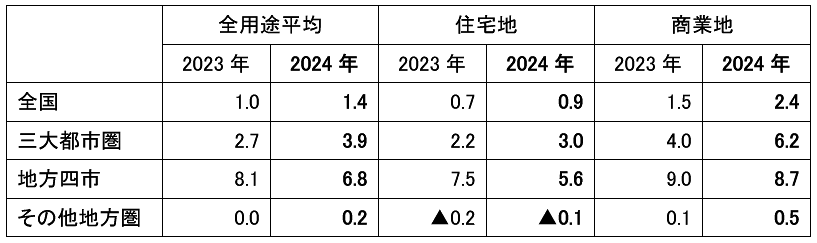
出典:国土交通省
三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)は、全用途平均で前年の2.7%から3.9%に上昇幅を拡大しています。用途別に見ると、住宅地が2.2% → 3.0%、商業地は4.0% → 6.2%と商業地の伸びが大きくなっています。
一方、地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)では、住宅地が7.5% → 5.6%に、商業地は9.0% →8.7%へと上昇幅が縮小しましたが、それでも三大都市圏を凌ぐ高い上昇率を維持しています。
その他の地方圏では、全用途平均は1992年以来32年ぶりの上昇となりました。住宅地では下落幅が縮小し、商業地は2年連続で上昇し上昇幅が拡大しています。
1-3. 半年ごとの動きでは2023年後半に上昇が加速
また2023~2024年の地価動向を前半・後半に分けて見ると、地方圏の住宅地を除き、前半よりも後半の上昇率が高くなっています。都市圏では上昇の勢いがまだ衰えておらず、地方圏では上昇がやや落ち着きつつあるとみることができます。
■ 半年ごとの変動率推移(前年比%)
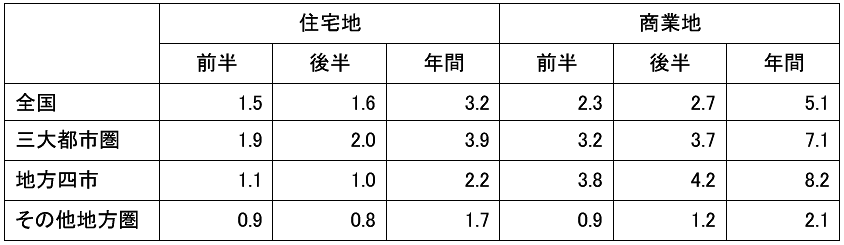
※出典:国土交通省
前半:2023年7月1日~2024年1月1日の変動率
後半:2024年1月1日~2024年7月1日の変動率
名古屋・大阪圏(住宅地)の上昇率上位の地点を見てみましょう。上昇率は大阪圏よりも名古屋圏の方が高く、名古屋市千種区、大府市、一宮市など、都心部から少し離れたベッドタウンが上位となっています。大阪圏ではインバウンドの回復により1位、2位は京都市がラインクインしていますが、3位以下は大阪市中心部に近いエリアが上位を占めています。
■住宅地の上昇率上位地点


2. 東海圏の基準地価、駅別ランキング
このように地価の上昇が続く中で、住宅購入にもっとも影響がある「住宅地」の地価について詳しく見ていきましょう。今回は東海圏(静岡・愛知)と関西(大阪府)の地価上昇率を駅別にランキングしてみました。
※基準地価は、住宅地の駅ごとの基準地価の平均で、㎡あたりの金額(円)です。
※集計対象は、駅から5km以内かつ前年との比較可能な地点です。
※「前年比(%)」は、駅ごとの平均地価で算出しています。地点ごとの前年比を平均したものではありません。
2-1. 東海圏で地価が上昇した駅は全体の70%
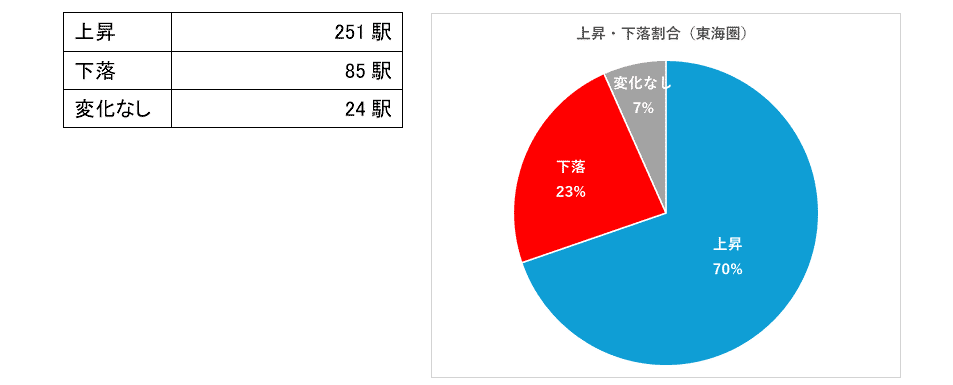
大阪府では、東海エリアよりも多い、8割以上の駅が上昇しています。
2-2. 大阪府の上昇率トップは福島駅。JR環状線と大阪メトロ沿線が強い
それでは、関西(大阪府)の上昇駅と下落駅のトップ20を見てみましょう。
■2024年基準地価 駅別上昇率トップ20(大阪府・住宅地)
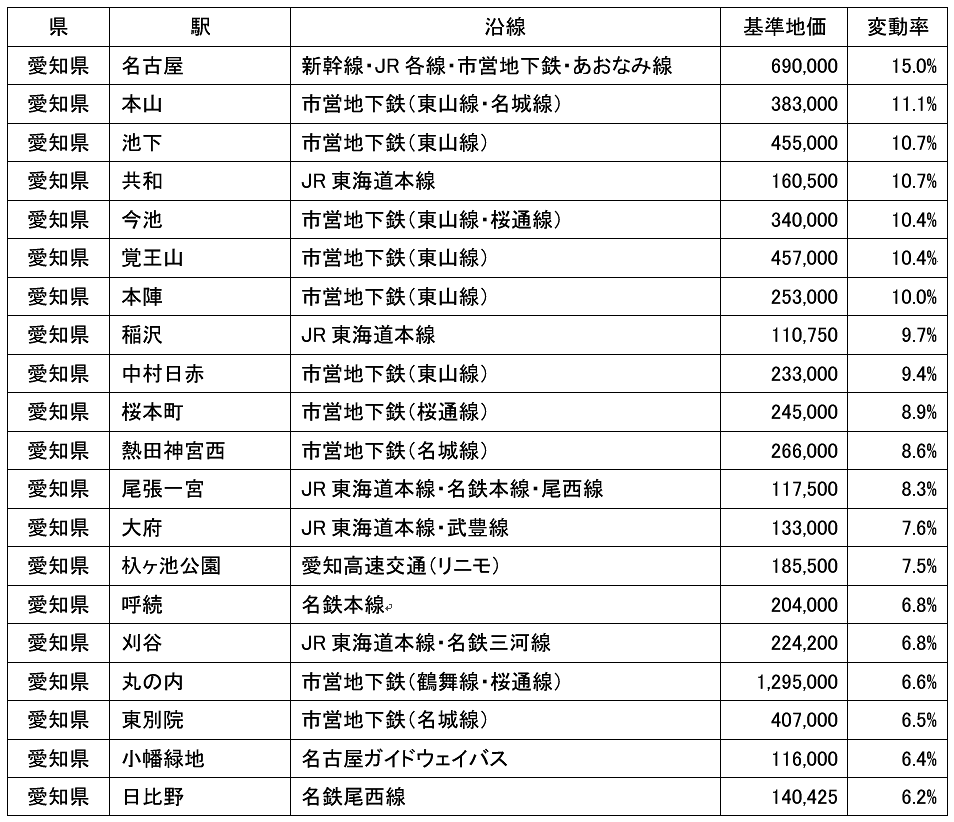
上表の通り、上昇率トップ20はすべて愛知県の駅が占める結果となりました。
トップは名古屋駅。言わずと知れた東海エリアの中心駅で、上昇率は15.0%と大幅な上昇となっています。2位以下には市営地下鉄の駅が多くランクインしており、上位20駅のうち10駅を占めています。その中でも名古屋市を東西に走る東山線の人気が高く、名城線とのクロスターミナルである本山駅、桜通線とのクロスターミナルである今池駅などが上位となっています。
また市営地下鉄と並んで上昇率が高いのがJR東海道本線ですが、4位の共和駅は名古屋市の南側に位置する大府市の駅です。また8位の稲沢駅(稲沢市)、12位の尾張一宮駅(一宮市)は、名古屋市の北側に位置する駅で、いずれも名古屋のベッドタウンとして人気の高い街です。
総じて言えば、交通アクセスも住環境もよい市営地下鉄沿線と、少し距離はあるけれど価格の安いJR東海道本線沿線の上昇率が高くなっていると見ることができます。
名古屋周辺は、JR、地下鉄、名鉄など多くの路線が乗り入れており、地下鉄と名鉄など、複数の路線が利用できるエリアも多くあります。また、名古屋市外からでも中心部まで15分~30分ほどでアクセスできるので、今後郊外のターミナル駅などの人気も高まってくると思われます。
2-3. 上昇率ワースト20には、三河エリア沿岸部や静岡県の山間部の路線がランクイン
次に、東海圏の上昇率ワースト20を見てみましょう。
■2024年基準地価 駅別上昇率ワースト20(東海圏・住宅地)
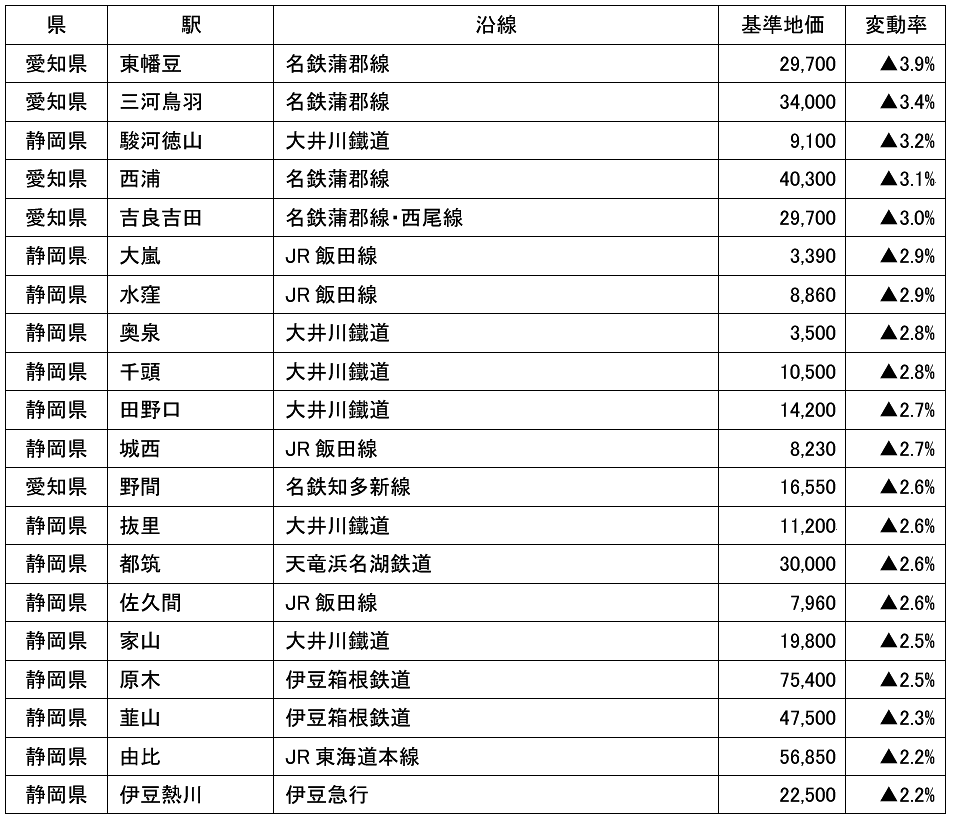
ワースト20は、愛知県の三河エリアを走る名鉄蒲郡線、静岡県の山間部を走る観光列車の大井川鐵道、同じく山間部を走るJR飯田線、伊豆半島を走る伊豆箱根鉄道などがランクインしています。いずれも都市部からはかなり遠く、観光地の色合いが強いため、一般の方が住宅を購入する対象にはなりにくく、今後も地価は下落傾向が続くと思われます。
2-4. 静岡県の地価上昇率が高い駅トップ10
東海エリアはトップ20がすべて愛知県のため、ここで静岡県の上位駅も確認しておきましょう。
■2024年基準地価 駅別上昇率トップ10(静岡県・住宅地)
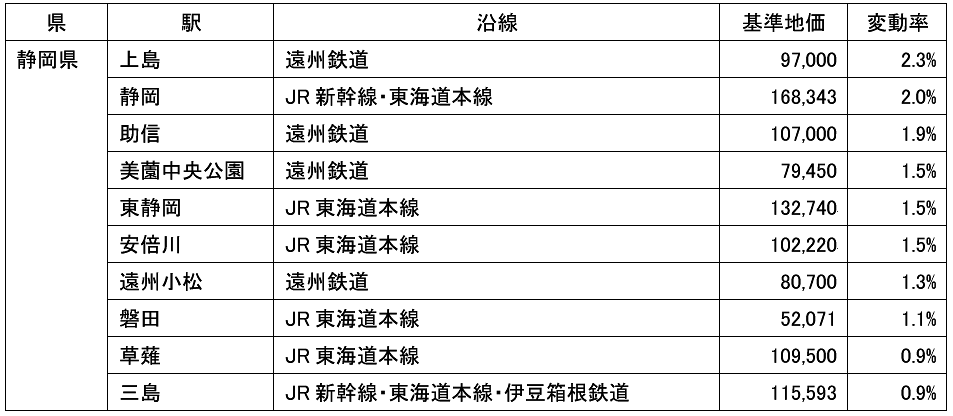
静岡県の上位は、新浜松駅を起点に市を南北に結ぶ遠州鉄道と、県内を東西に走るJR東海道本線が占める結果となっています。トップの上島駅は新浜松駅から6駅、3位の助信駅は新浜松駅からたった4駅という好立地にあり、浜松駅へのアクセスが地価上昇の決め手となっているようです。また東海道本線は、新幹線停車駅である静岡駅が2位、隣駅の東静岡駅と安倍川駅がそれぞれ5位と6位に、東静岡駅の隣駅である草薙駅が9位にランクインしています。
静岡県は、静岡駅と浜松駅が2大都市圏となっているため、おのずとこの両駅に隣接するエリアが地価上昇の中心となるのでしょう。

3. 関西(大阪府)の基準地価、駅別ランキング
続いて関西エリア(大阪府)のランキングを見てみましょう。
3-1. 関西(大阪府)で地価が上昇した駅は全体の69%
対象となる駅のうち、前年比で上昇・下落している割合は次の通りです。
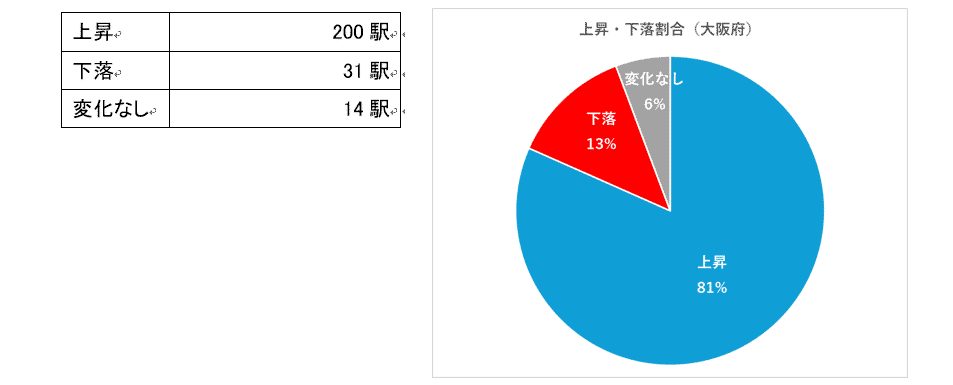
大阪府では、東海エリアよりも多い、8割以上の駅が上昇しています。
3-2. 大阪府の上昇率トップは福島駅。JR環状線と大阪メトロ沿線が強い
それでは、関西(大阪府)の上昇駅と下落駅のトップ20を見てみましょう。
■2024年基準地価 駅別上昇率トップ20(大阪府・住宅地)
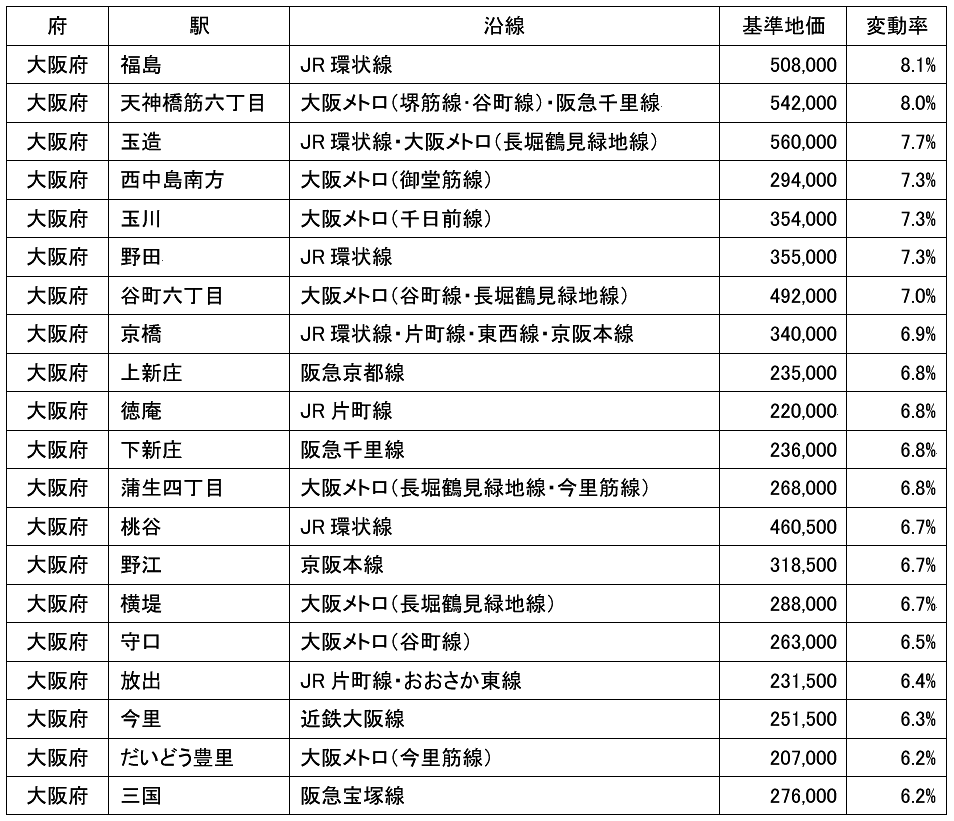
上表の通り、上昇率トップ20はほぼ大阪市内の駅が占める結果となりました。トップの福島駅は大阪駅に隣接する駅で、中高層のマンションやビルが建ち並ぶエリアです。2位以下も、比較的中心部に近い駅がランクインしており、戸建の住宅地というよりは、マンション需要、インバウンド需要の強さが地価の上昇につながっていると思われます。
一方、9位以下には戸建メインの住宅地もランクインしてきます。9位の上新庄駅、11位の下新庄駅は阪急千里線沿線、10位の徳庵駅(東大阪市)はJR片町線沿線の低層住宅地です。上位の駅と比べると価格も㎡あたり20万円台まで下がりますので、比較的購入しやすいエリアと言えそうです。
3-3. 上昇率ワーストは、大阪府南部のJR阪和線と南海沿線が多くランクイン
次に、関西(大阪府)の上昇率ワースト20を見てみましょう。
■2024年基準地価 駅別上昇率ワースト20(大阪府・住宅地)
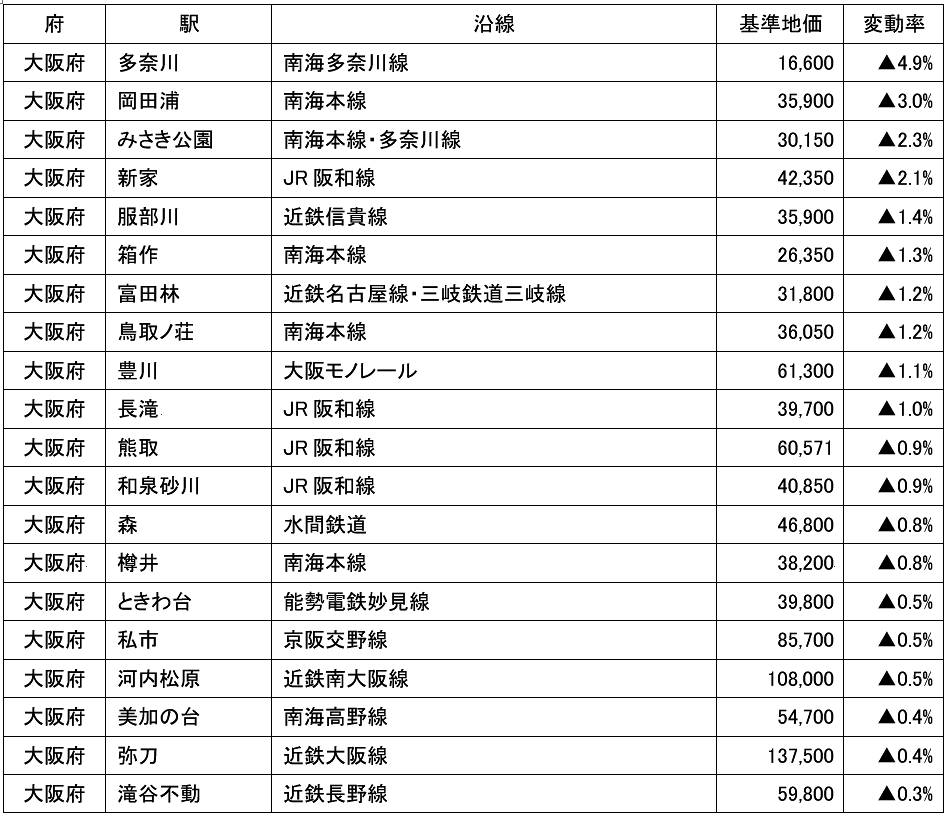
ワースト20の上位は、大阪府南部の南海沿線とJR阪和沿線がランクインしており、下落率も▲2~4%と大きくなっています。また下落率はそれほど大きくないものの、奈良に近い河内地方の近鉄大阪線・長野線もランクインしています。
大阪府の地価上昇は、ほぼ大阪市とその周辺エリアに偏っており、南部と東部は今後も下落傾向が続くと予想されます。

4. 2024年の基準地価は上昇を加速。名古屋、大阪圏では都心部が強い
東海・関西圏の2024年基準地価の駅別ランキング、いかがでしたでしょうか。
駅別の地価動向は、市区町村別よりも上昇・下落をより細かく、沿線ごとの動向も見ることができるので、物件を選ぶ上で大いに参考になるのではないかと思います。
4-1. 名古屋、大阪では新幹線駅を中心に、都市部の地価上昇が続く
前回の首都圏版では、地価の上昇が都心部から郊外に広がっている傾向があるとお伝えしましたが、東海・関西圏においては、まだまだ都心部の上昇率が高く、都心部から放射状に走る地下鉄沿線の人気が高いようです。
これは、首都圏では近郊に横浜や大宮といった大都市が存在するのに対し、愛知県では名古屋、静岡県では静岡や浜松、大阪府では大阪(梅田)といった中心駅に職場や学校が集中していることが要因かも知れません。また地価が東京ほど高くないので、電車で15~30分ほどの近郊エリアでも購入しやすいのがひとつの要因と考えられます。
4-2. 将来の発展が期待できる沿線をしっかり見極めよう
こうした駅選びとともに、注意しておきたいのが沿線選びです。上記のランキングをみても分かる通り、地価が上昇する沿線と下落する沿線にはかなりの偏りがあります。
愛知県であれば市営地下鉄と東海道本線、静岡県であれば遠州鉄道と東海道本線、大阪府であれば市営地下鉄と環状線など、人気の高い沿線を選ぶのが住まい選びのポイントとなります。
人気の沿線には人が集まり、将来的な発展が期待できますが、人気のない沿線は人口が減り、徐々に街が廃れていきます。列車の本数が減少したり、特急などが止まらなくなったりと、沿線選びを間違えると、将来にわたり不便を強いられることにもなりかねませんので注意しましょう。これから住宅を購入する方は、人気のある沿線・駅の見極めをしっかりとおこないながら、物件探しを進めていきましょう。
本記事のランキングにない沿線・駅の情報などは、お近くの住宅情報館までお気軽にお問合せください。


.png)