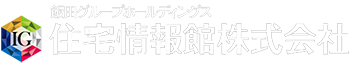20代の持ち家率が過去最高となっています。コスパに厳しいZ世代でマイホームの購入が増えているのはなぜなのか?そこには不動産を「資産形成」の一環と考える動きがあるようです。今回はマイホームの購入年齢による資産形成の差について検証してみました。
目次
1. Z世代はモノを持たずにコスパ重視。でも住まいだけは別?
1990年代後半~2000年代前半生まれのいわゆるZ世代は、モノの所有にこだわらず、コスパ重視でムダなお金を使わないと言われますが、住まいだけは別のようです。若い世代の住宅購入が増える背景を見てみましょう。
1-1. 20代の「持ち家率」が上昇し過去最高に
2024年3月22日の日経新聞の記事によれば、世帯主年齢29歳以下の2人以上世帯の持ち家率が上昇しており、2023年は35.2%と過去最高になりました。実に20代の3世帯に1世帯以上がマイホームを購入していることになります。
要因としては、近年の不動産価格の値上がりで、不動産を(値上がりが期待できる)資産ととらえ、資産形成の一環として購入する人が増えていること。また、収入の増加や低金利なども、若い世代の住宅購入の追い風となっていると言われています。
1-2. 将来の売却や住み替えを検討する割合も上昇
また、リクルート社が発表した「住宅購入・建築検討者』調査(2023年)」によると、住宅購入検討者の「永住志向」にも変化の兆しが現れています。
これまで、住まいは「一生に一度の買い物」と言われることもありましたが、この調査では、「将来的に売却を検討している」層が、2022年の24%から、2023年の31%へと大きく増加しており、全体の約1/3にのぼることがわかりました。
1-3. 若い世代の住まい購入が増える背景
こうした変化の背景には「不動産=資産」という意識が大きく影響しています。これまで住宅購入の中心だった30代後半~40代は、バブル崩壊後の不動産価格の下落を間近で見てきた世代であり「不動産=リスク」という意識を強くもっています。
しかしZ世代は、2013年に始まったアベノミクス以降の不動産価格の上昇を間近で見ている世代です。加えて、生まれた時からインターネットのある世界で育っていますので、資産運用などに関する知識も豊富で、NISAの活用などにも積極的です。またZ世代はモノを持たないと言われますが、自分の好きな趣味などにはお金を惜しまず、たくさんの選択肢を比較してコスパのよいモノを選ぶ傾向があるとも言われます。
こうした背景のもと、20代の住宅購入が増えているのは、「住まい=コスパのいい投資」だと考える人が増えているからに他なりません。言い換えれば、「ずっと賃貸に住んでいるより、早く買ったほうが得」と考える人が増えているわけです。
今回のコラムでは、20代で住まいを購入するメリットや、購入年齢によって、その後の資産状況がどう変わってくるのかなどについて検証してみます。

2. 20代で住まいを買うメリットとは?
まず、20代で住まいを購入する一般的なメリットについて見ていきましょう。
2-1. 定年前に住宅ローンを完済できる
住宅ローンの返済期間は、一般的に最長35年です。仮に28歳で購入したとすれば、ローンの完済年齢は63歳。定年前にローンの返済を終えることができます。一方、40歳で購入した場合の完済年齢は75歳。65歳定年とすれば、その後10年間返済を続けるか、退職金などで一括返済するしかありません。
定年前にローンを完済できれば退職金をまるまる手元に残し、マイホームにずっと住み続けることができるわけです。またローンを完済していれば、住まいを売却して住み替えるなど老後の選択肢が大きく広がります。
2-2. 住宅ローンの返済期間が長くできる
一般的に住宅ローンは「完済時年齢」が決められており、多くの金融機関で80歳を超える返済期間は設定できません。しかし現実的には80歳まで返済を続けることは難しいので、実際には70歳くらいを目安に返済計画を立てることになるでしょう。仮に70歳完済とすれば、35年ローンを組めるのは35歳まで。もし40歳で購入するとすれば返済期間は30年になります。
住宅ローンは、返済期間が短くなるほど月々の返済額が増えます。返済負担の軽い長期のローンを利用するなら若いうちの方が有利になります。
2-3. 賃貸の家賃負担が少なく済む
住まいを購入するまでの間、多くの方は賃貸住宅を借りることになりますので、早く購入するほど、支払う家賃は少なくて済みます。
例えば、月12万円の賃貸マンションにかかる家賃は年間144万円。5年間ならば720万円、10年間ならば1,440万円と、たった5年間でも大きな差になります。駐車場代や更新料なども含めれば、さらに金額は増えますので、賃貸の居住期間が短くなるのは大きなメリットと言えます。
2-4. 子どもの転園や転校を気にしなくていい
30~40代になってからの住宅購入では、子どもの転園や転校という問題が生じます。もし転校させたくないとなれば、物件を選べるエリアはかなり限定されますので、物件が見つからないというケースも出てくるでしょう。そうなれば、購入は卒業まで待たねばならず、家賃負担はさらに増えることになります。子どもが産まれる前か入園前に、広い範囲で物件を選べるのは大きなメリットなのです。
2-5. 若いうちに住まいを購入するデメリット
このように、若いうちに住まいを購入することには多くのメリットがある反面、デメリットもあります。例えば、賃貸と比較して気軽に転居しにくくなることや、収入が低い分、借入可能額が少なくなるなどが挙げられます。
しかし前述の通り、最近では買った価格より高く売れるケースも増えてきており、必ずしも転居しにくいとは言えません。また、共働き夫婦の場合は、2人の収入を合算することで借入額を増やすことも可能です。

3. 「20代vs 40代」住まいの購入年齢で資産はどう変わるのか?
それでは具体的に20代で購入したケースと40代で購入したケースを比較して、資産状況にどのような違いが生まれるのかを検証してみましょう。
3-1. 家賃とローン返済の違いとは?
住宅を購入した場合「家賃を支払わなくてよい代わりに住宅ローンを返済しなければならないので結局同じじゃないか?」という声をよく耳にします。しかし、家賃とローン返済はその性格がまったく異なります。まず両者の違いから見ていきましょう。
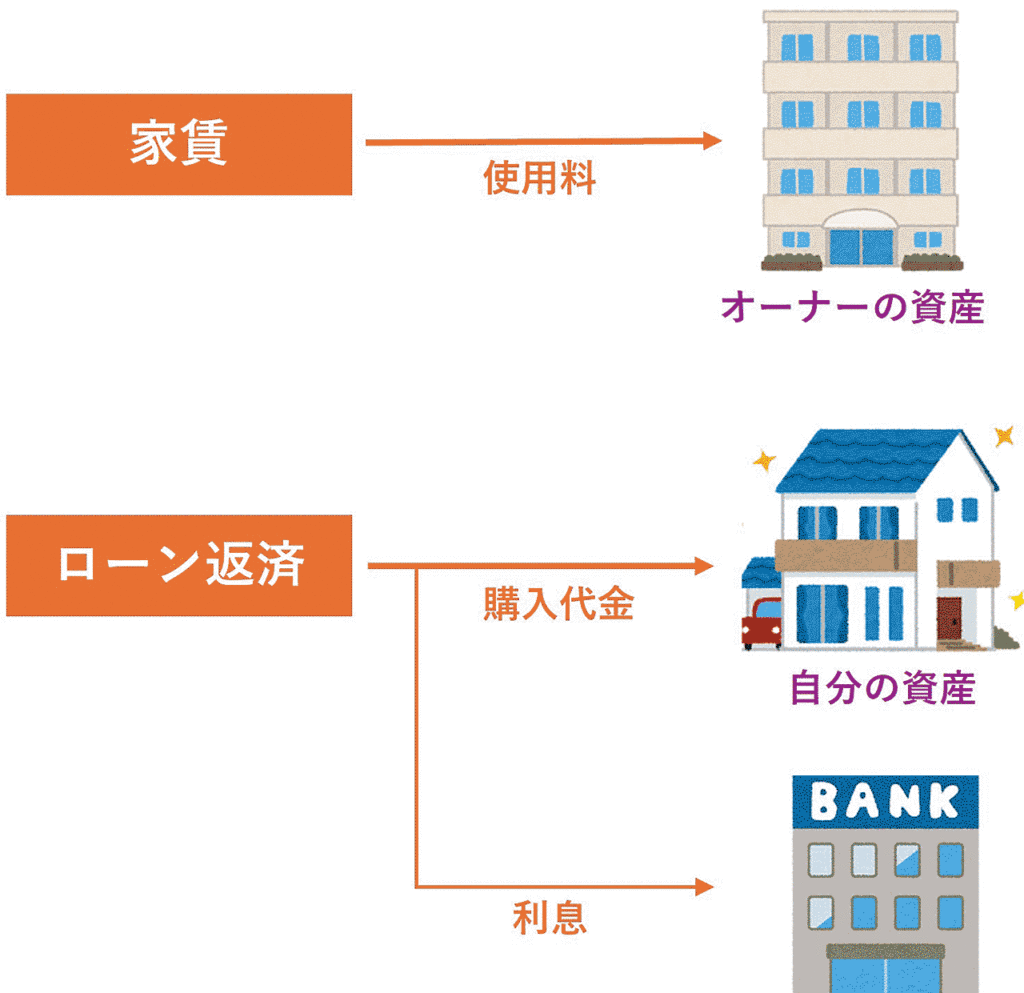
上図のように、賃貸の家賃はオーナーに対して支払われます。賃貸マンションはオーナーの資産であり、その使用料を支払っているに過ぎませんから、いくら支払っても自分の資産が増えることはありません。つまり100%コストとなります。
一方ローン返済は、自分の資産を購入するための代金と利息ですので、ローンを完済すれば自宅という資産が残ります。また返済中であっても自由に売却できますので、想定される売却金額からローンの残債を引いた分は自分の資産と言えるでしょう。つまり、ローンの返済が進むほど自分の資産は増えていき、100%コストになるわけではありません。これが家賃とローン返済の一番大きな違いです。
3-2. 住宅購入年齢が28歳と40歳の場合の資産比較
それでは具体的に見てみましょう。28歳でマイホームを購入したAさんと、40歳でマイホームを購入したBさんの資産推移を比較してみます。シミュレーション条件は以下の通りです。
| 賃貸 | 家賃 月12万5,000円(更新料等は考慮しない) |
| 購入 | 価格 4,500万円(諸経費等は考慮しない) ※30年目まで、購入価格の年1%の割合で資産価値が減価するものとする ※ローン借入額4,500万円 金利1.0% 35年返済(ボーナス払いなし) |
このケースだと、家賃支払いは月12万5,000円(年間 150万円)、ローン返済は月12万7,000円(年間 約152万円)なので、現金支出はほぼ同額となります。
一方、年齢ごとの資産(不動産)と負債(ローン残債)の関係はどうなるでしょうか?
28歳で購入したAさんから見ていきましょう。
■Aさん(28歳で購入)
| 年齢 | ①28歳からの 累計支出 | ②資産 | ③負債 | ④正味資産 (②-③) |
| 30歳 | 456万円 | 4,410万円 | 4,172万円 | 238万円 |
| 40歳 | 1,976万円 | 3,960万円 | 3,009万円 | 951万円 |
| 50歳 | 3,496万円 | 3,510万円 | 1,723万円 | 1,787万円 |
| 60歳 | 5,016万円 | 3,195万円 | 301万円 | 2,894万円 |
| 70歳 | 5,320万円 | 3,195万円 | 0万円 | 3,195万円 |
まず30歳時点での状況を見てみましょう。購入から3年で456万円をローン返済に支出していますが、所有する資産(自宅)が4,410万円、負債(ローン残債)が4,172万円ですので、資産から負債を引いた正味資産は238万円となります。
同様に40歳時点では1,976万円の支出に対して、正味資産が951万円。
60歳時点では5,016万円の支出に対して、正味資産2,894万円となり、支出した金額の約58%が自分の資産になっていることがわかります。
一方、40歳で購入したBさんはどうなるでしょう。
■Bさん(40歳で購入)
| 年齢 | ①28歳からの 累計支出 | ②資産 | ③負債 | ④正味資産 (②-③) |
| 30歳 | 450万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
| 40歳 | 1,952万円 | 4,500万円 | 4,392万円 | 108万円 |
| 50歳 | 3,472万円 | 4,050万円 | 3,251万円 | 799万円 |
| 60歳 | 4,992万円 | 3,600万円 | 1,990万円 | 1,610万円 |
| 70歳 | 6,512万円 | 3,195万円 | 597万円 | 2,598万円 |
Bさんは、30歳時点では賃貸に住んでおり、Aさんとほぼ同額の450万円を家賃に支出していますが、賃貸なので資産・負債ともゼロになります。
住まいを購入した40歳時点では、家賃と返済を合わせた1,952万円の支出に対して、正味資産は108万円。
60歳時点では4,992万円の支出に対して、正味資産は1,610万円となり、支出した金額の約32%しか資産になっていません。
下のグラフは、AさんBさんの累計支出額と正味資産の推移を表したものです。
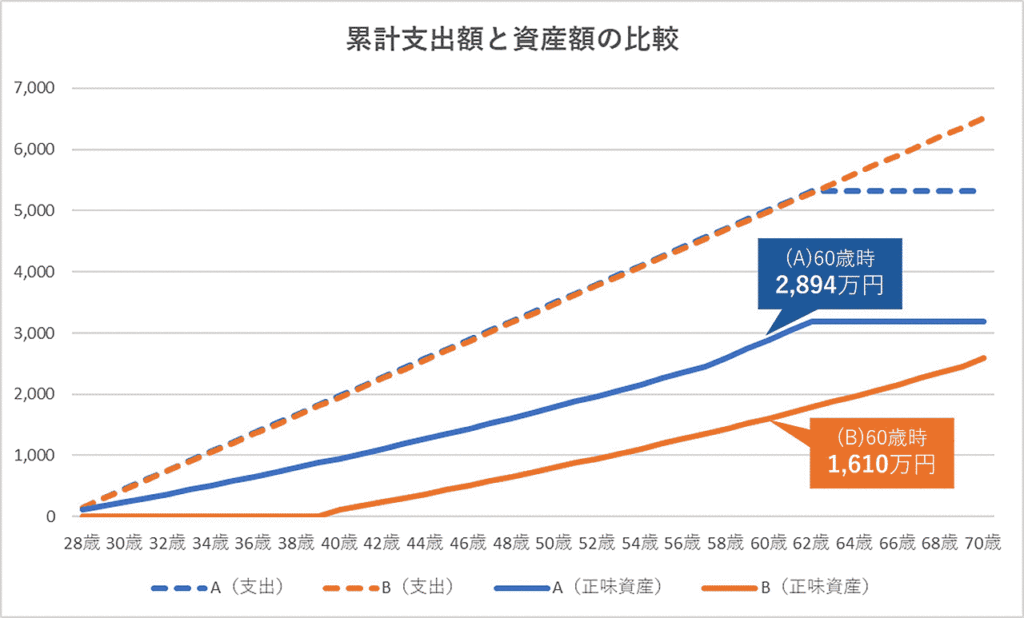
まず支出額(点線)から見ていくと、63歳までAさんとBさんの支出額はほとんど変わりません。(Aさんは63歳でローンを完済するので、それ以降横ばいになります)
それにもかかわらず、正味資産額は、28歳で購入したAさんと40歳で購入したBさんで大きな差があるのがわかります。Bさんは28~40歳までの12年間、賃貸で家賃を支払い続けていたため資産形成が進まず、60歳時点での資産に1,200万円以上の差が開いてしまったことになります。しかも、Aさんは63歳でローン返済が終了しますが、Bさんは75歳まで返済が続きます。
3-3. もし不動産価格が上昇したらどうなる?
さらに、購入した不動産の価格が上昇した場合にはどうなるでしょうか?
前項のシミュレーションは、価格が30年目まで、毎年購入価格の1%下落することを前提としていましたが、逆に毎年購入価格の0.5%ずつ上昇するとした場合のグラフが以下になります。
-1024x618.gif)
青のAさんは支出額(点線)と正味資産額(実線)の差がほぼなくなり、支出した金額のほとんどが資産になっていることがわかります。
60歳時点での累計支出額5,016万円に対して正味資産額は4,852万円、実に支出額の96%が資産となっています。またこの時点で、値上がりにより自宅の資産価値は5,153万円に増え、ローン残債は301万円まで減っていますから、売却すれば4,800万円近くの利益が出ることになり、いつでも住み替えが可能になります。
またBさんも値上がりにより資産は増えていますが、賃貸居住中の12年間は値上がりのメリットを得られていないので、Aさんとの差は約1,900万円まで広がっています。
3-4. 若い時期からの資産形成は住み替えの自由度を高める
上記の例は少し極端かもしれませんが、冒頭に申し上げた「不動産=資産」という意味がご理解いただけるでしょうか?
日本がデフレからインフレに向かおうとしている今だからこそ、「自宅」という不動産を資産ととらえ、若いうちから資産形成に取り組む意味があると言えます。
そしてグラフからもわかるように、早く始めれば始めるほど、資産形成のスピードは早まります。50~60代にいつでも売却して利益が出せる自宅があるということは、住み替えの自由度を高め、その後の人生の選択肢を大きく広げることにもつながります。

4. 20代の住宅購入はリスクよりメリットの方が大きい
20代で住まいを購入するメリット、いかがでしたでしょうか?
最後に資産形成という観点から見た20代でマイホームを購入するメリットについてまとめます。
4-1. 資産形成という観点から見た住宅購入のメリットまとめ
ここまで見てきたように、資産形成という観点から見た20代での住宅購入のポイントは以下の通りです。
1. 賃貸でも購入でも、支出する金額に大きな差はない(もちろん物件による)
2. 賃貸の家賃はすべてコストとなり、いくら払っても資産として残らない
3. 住宅ローンの支払いは、支出した額の何割かが資産となる
4. 20代で購入すれば、40~50代で1,000万円以上の資産を保有することも可能
5. 自宅の資産価値がローン残債を上回れば、いつでも売却・住み替えが可能に
6. 定年前にローンを完済できれば、退職金を残せて、老後の安定につながる
4-2. 住まいの購入に「資産形成」という観点を
不動産価格が上昇し、本格的な金利上昇が迫る中、住宅購入をためらう声も聞かれますが、若い世代では、住宅を資産ととらえ、株式や投資信託と同じように早いうちから資産形成に取り組む動きが始まっています。
また、日本は今後ゆるやかなインフレが続くとも予想されています。これからのマイホーム購入は、ローンの「支出」だけに目を向けるのではなく、低利のローンを上手に使いながら「資産」を増やしていくという発想が大切になります。
だからこそ、長期にわたって値下がりしにくい、願わくは値上がりが期待できるエリア選び、物件選びがますます重要になってきます。
資産形成を意識した物件選び、20代でも利用できる住宅ローンのご相談などはお近くの住宅情報館までお気軽にご相談ください。


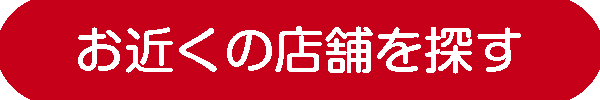


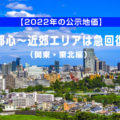

-120x120.jpg)