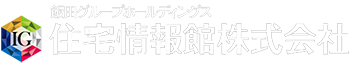住まいを購入する際の、重要な判断材料のひとつは「価格」です。しかし、立地も広さも違う物件を比較して、その価格が妥当かどうかを判断するのは難しく、多くの方が「ローンを返済できるかどうか」で判断されているようです。そこで今回は、不動産の適正価格と一般の方でもできる価格の比較方法について解説します。
目次
1、そもそも不動産の適正価格とは?
まず、不動産の適正価格とは何なのかということについて考えてみたいと思います。
1-1. 不動産に絶対的な適正価格はない
こう言ってしまうと身も蓋もありませんが、不動産に絶対的な適正価格というものはありません。不動産は1つとして同じものが存在しないので、家電や洋服のように「同じモノなら原則として同じ価格」という前提が成り立たず、加えて、その時々の需給関係や経済情勢(景気や金利など)などによって常に価格が変動しているからです。しいて言えば「取引が成立した価格 = 適正価格」ということになります。
1-2. 過去の取引事例と比較することで、ある程度、適正価格かどうかはわかる
では、これから住まいを購入しようという方は、どうやって価格の妥当性を確認すればよいのでしょうか。それは条件が類似した、より多くの物件と比較してみることです。前述のように不動産の適正価格は、実際に取引が成立した価格と言えますが、こうした過去の取引事例を多く集め、比較してみることによって、ある程度、価格の妥当性は検証できます。ではどうやって比較すればいいのか、事例はどのように集めるのかを具体的に見ていきましょう。
2、不動産の適正価格を調べるための比較方法とは
まず、不動産価格の比較方法について見ていきましょう。
2-1. 何と比較すればいいの?
価格の妥当性を判断するための比較対象としては、以下のようなものが挙げられます。
①物件周辺の取引事例や売出し中の物件
最もわかりやすく納得感があるのは、購入検討している物件の周辺の取引事例と比較することです。マンションであれば同じ棟の住戸や、間取りや方位が似た住戸、一戸建であれば、同じ区画で土地や建物の広さが近いもの、建物の構造や築年数が近いものなど、できるだけ条件の近い事例が集められるとよいでしょう。また、取引時期が最近の事例ほど比較しやすくなります。
周辺に取引事例がなければ、ポータルサイト等で売出し中の物件を探して、おおよその見当をつけることもできます。ただ、売出し価格はあくまでも売主の希望価格であり、実際に取引が成立した価格ではありませんのでやや注意が必要です。
②新築時の販売価格
中古物件の場合には、新築時の販売価格も比較対象になります。新築時の販売価格から築年数による減価分、不動産市場全体の推移、金利差などを考慮して、おおよその適正価格を求めることが可能です。
③公表されている公示地価や基準地価
土地の価格は、不動産鑑定士による評価をもとに、国や都道府県が目安となる取引価格を公表しています。1月1日時点の「公示地価」、7月1日時点の「基準地価」は実勢価格に近く、価格の動きを知る上でも参考になりますが、公表されるのは地域ごとの代表的な地点のみとなります。一方、相続税の評価にも使われる「路線価」は、市街地のほぼすべての地点に対して公表されますので、より正確に比較できます。ちなみに路線価は公示地価の8割程度とされていますので、比較する際は「路線価÷0.8」で実勢価格に割り戻すようにしましょう。
2-2. どうやって比較すればいいの
次に取引事例や公示地価などと、どのように比較したらよいのかを見てみましょう。ポイントは大きく2つです。

① 1㎡あたりの価格で比較する
1つめのポイントは、「1㎡あたり」に換算して比較することです。一般的に「㎡単価」と呼ばれますが、価格を面積(㎡)で割って算出します。この場合の面積は、土地は「土地面積」、建物は「延床面積」、マンションの場合は住戸の「専有面積」を使用しましょう。いずれも不動産の広告には必ず記載されています。また、不動産業界では1坪(約3.3㎡)あたりの価格である「坪単価」もよく使われます。
②土地と建物を分けて比較する
一戸建の場合には、価格を土地と建物に分けて比較しましょう。どのように分けるかは後述しますが、土地と建物が合算された「販売価格」だけでは比較しにくいですし、妥当かどうかはなかなか判断できません。
2-3. 過去の取引事例はどうやって調べればいいの
過去の取引事例を調べるには、インターネット等を使って自分で調べる方法と、不動産会社に依頼する方法があります。自分で調べるには、国土交通省が運営する「不動産取引価格情報検索」や、全国指定流通機構連絡協議会が運営する「REINSマーケットインフォメーション」等を利用すると便利です。
これらのサイトでは、全国の不動産の取引事例を検索することができますが、すべての取引が掲載されているわけではありません。また、町名までしか表示されないので、特定の物件をピンポイントで調べることはできません。
一方、不動産会社に依頼すると、不動産会社専用のネットワークシステム「REINS」や、提携しているデータ提供会社から、一般には公開されていない取引事例や、新築時のパンフレット・価格表などを入手できる場合があります。ご自身で調べるのが難しいという方は相談してみるとよいでしょう。
2-4. 不動産市場の推移を調べる方法
前述の通り、不動産の価格は常に変動していますので、過去の取引事例と現在の販売価格を比較する時には、不動産市場全体の変動を加味する必要があります。例えば新築マンションが10年前に3,000万円で販売されていて、現在、同程度の新築マンションが3,600万円で販売されている場合、一見すると「高いなあ」と感じるかも知れませんが、マンション市場全体が20%上昇していたとしたら、それは適正な価格と推測することができます。
不動産価格の推移は国土交通省が公表している「不動産価格指数」で調べることができます。このデータから、2013年以降、マンションは価格高騰が続いていることがわかります。
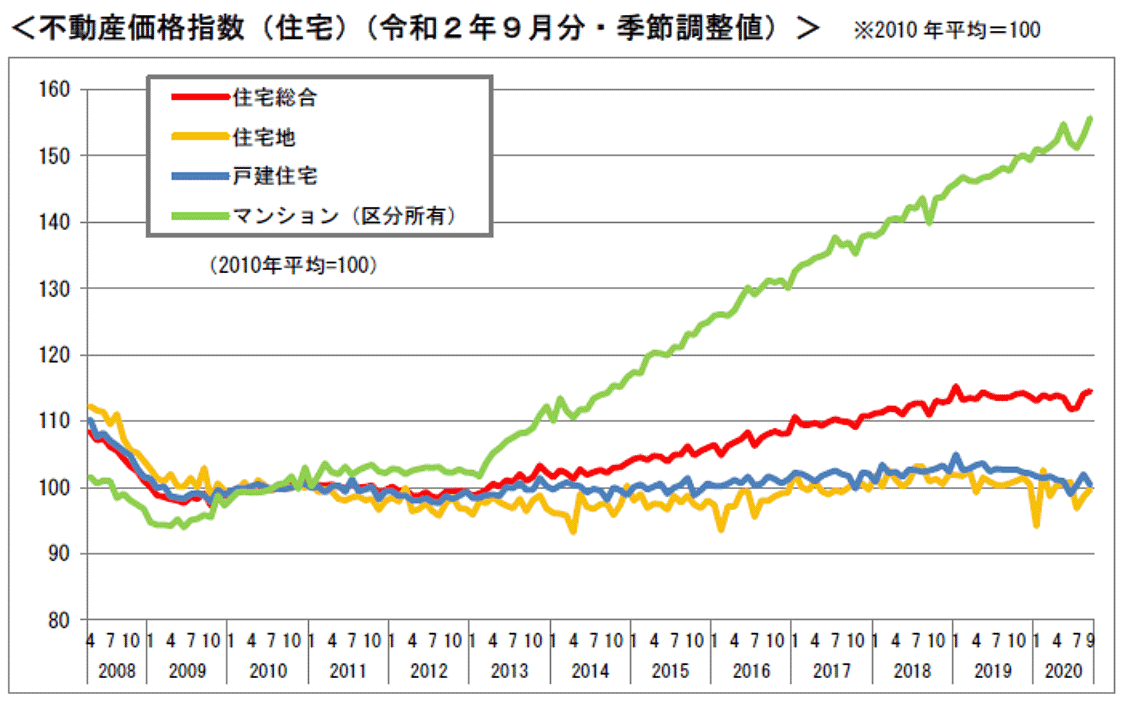
出典:不動産価格指数(国交省)
※2010年の平均価格を100として、価格の推移を毎月発表しています。
3、土地と建物の価格を分けて比較する方法
最後に一戸建の土地・建物の価格を分けて比較する方法をご紹介します。
3-1. 新築一戸建の場合
新築一戸建の場合、不動産会社が販売する物件は、販売価格に建物の消費税が含まれています。したがって、消費税額が分かれば簡単に建物の価格を割り出すことができます。そして、販売価格から建物価格を引いたものが土地価格になります。(土地は消費税の課税対象外です)
[計算式]
建物価格 = (消費税額÷10%[消費税率])+消費税
土地価格 = 販売価格 − 建物価格
次に土地、建物それぞれの「㎡単価」を計算してみましょう。土地は土地面積、建物は延床面積で割って算出します。
[計算式]
土地の㎡単価 = 土地価格÷土地面積(㎡)
建物の㎡単価 = 建物価格(税抜)÷ 延床面積(㎡)
ここまで計算できたら、土地は公示価格や基準地価と、建物は標準的な建築価額表などをもとに比較してみましょう。
■建物の標準的な建築価額表(円/㎡)
|
建築年 |
木造・
木骨モルタル |
鉄骨鉄筋
コンクリート |
鉄筋
コンクリート |
鉄骨 |
|
2014年 |
163,000 | 276,200 | 228,000 |
176,400 |
|
2015年 |
165,400 | 262,200 | 240,200 |
197,300 |
|
2016年 |
165,900 | 308,300 | 254,200 |
204,100 |
|
2017年 |
166,700 | 350,400 | 265,500 |
214,600 |
|
2018年 |
168,500 | 304,200 | 263,100 |
214,100 |
|
2019年 |
170,100 | 369,300 | 285,600 |
228,800 |
出典:「建築統計年報(国土交通省)」の「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表の1㎡当たりの工事費予定額による。
3-2. 中古一戸建の場合
個人所有の中古一戸建の場合には、消費税が課税されませんので、新築と同じ方法で土地と建物の価格を分けることはできません。この場合は、公示価格や路線価からおおよその土地価格を算出し、販売価格から土地価格を引いて、建物の価格を割り出します。
[例] 土地(100㎡)・建物(木造90㎡)の合計が2,500万円。公示地価が20万円/㎡の場合
土地価格 = 20万円×100㎡ = 2,000万円
建物価格 = 2,500万円(販売価格) – 2,000万円(土地価格) = 500万円(㎡単価 5.5万円)
このケースの場合、建物の㎡単価が、標準的な建築価額(約17万円/㎡)の約1/3に下がっています。木造の耐用年数は一般的に25年程度とされていますので、耐用年数の2/3が経過した築17年くらいの建物であれば、ある程度、妥当な金額と捉えることができるでしょう。ただし一戸建ては、もともとの建物のグレードやリフォームの有無、メンテナンス等によって、かなり価格に幅がありますので、最終的には個々の物件を見て判断することになります。

4、不動産の購入時には、ローン返済額だけでなく価格の妥当性を確認しよう
ここまで、不動産価格の妥当性、比較方法について解説しましたがいかがでしたでしょうか。
不動産を購入する際は、とかくローンの返済額だけに目がいってしまい、価格の妥当性をよく確認せずに購入判断をしてしまうことも多いようです。
過去の取引事例や不動産市場全体の動きなどと比較することで、現在の価格の妥当性だけでなく、将来的な資産価値もある程度わかるようになります。
ご自身で調べるのが難しいという方は、不動産会社のスタッフなど専門家に相談してみることをおすすめします。



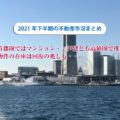
-120x120.jpg)