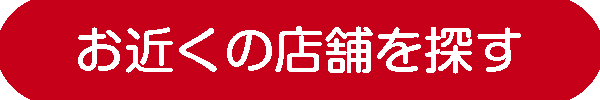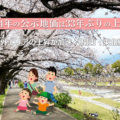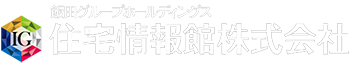3月26日、令和6年(2024年)の公示地価が発表されました。コロナ明けから上昇が続いていた地価は、全国平均で+2.3%と33年ぶりの高い上昇率となりました。前回の関東・東北編に続き、今回は東海・関西エリアの地価動向を詳しく見ていきましょう。
目次
1. 全国平均(全用途)は住宅地・商業地とも3年連続で上昇が加速
2024年公示地価の変動率は、全国平均(全用途)で前年の1.6%から2.3%へと上昇幅を拡大しました。用途別に見ても、住宅地(1.4% → 2.0%)、商業地(1.8% → 3.1%)とも大きく上昇し、コロナ前の水準を回復しています。
住宅地では、景気の緩やかな回復、低金利の継続、住宅取得支援施策などの背景のもと、都市中心部や、利便性・住環境に優れたエリアの住宅需要は依然として旺盛です。
また商業地も、観光・インバウンドなど人流の回復にともなう店舗需要、オフィス需要などに加え、再開発事業等が進展している地域での地価上昇も継続しています。
1-1. そもそも公示地価とは
公示地価とは、地価公示法に基づき、全国2万ヶ所以上の基準値の標準価格を、不動産鑑定士が調査し公表するものです。毎年1月1日時点の価格を3月下旬に発表しています。都道府県地価(基準地価)と同様、適正な地価形成を目的とし、土地取引の指標となる価格として活用されています。
1-2.三大都市圏は上昇幅を拡大。地方四市の住宅地は上昇幅が縮小するも+7%超
次に圏域別に直近1年間の地価動向を見てみましょう。
■2024年公示地価の変動率

※出典:国土交通省
三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)は、全用途平均で前年の2.1%から3.5%に上昇幅を拡大しています。用途別に見ると、住宅地が1.7% → 2.8%、商業地は2.9% → 5.2%と商業地が大きく上昇しています。
一方、地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)では、住宅地が8.6% → 7.0%に上昇幅が縮小しましたが、それでも三大都市圏を凌ぐ高い上昇率を維持しており、商業地は8.1% →9.2%と上昇幅を拡大しています。
コロナ明けから3年連続の上昇となった地価は、バブル以来の高い上昇率を記録しました。その中でも、人流の回復にともなう商業地の上昇率が大きく伸びているのが2024年の特徴と言えるでしょう。
1-3. 半年ごとの動きでは2023年後半に上昇が加速
また2023年の地価動向を前半・後半に分けて見ると、住宅地・商業地とも、地方圏の一部を除き、前半よりも後半の上昇率が高く、上昇の勢いが加速していることがわかります。
■ 公示地価の半年ごとの変動率推移(前年比%)
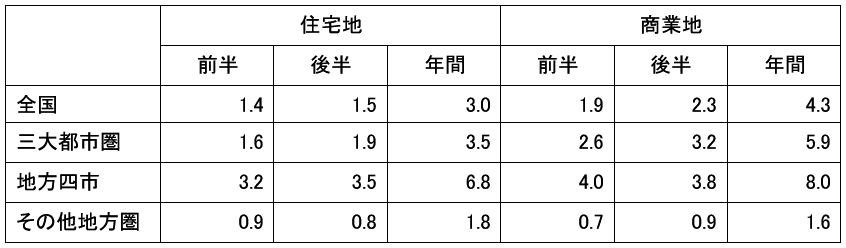
※出典:国土交通省
※前半:2023年1月1日~2023年7月1日の変動率 / 後半:2023年7月1日~2024年1月1日の変動率
また地点ごとの上昇率を見ると、前年からの上昇幅が大きい地点に近郊~郊外エリアが多数含まれることから、上昇の波が都心部から郊外に広がりつつあることがわかります。
圏域ごとの上昇率上位を見ると、名古屋圏のトップは、名古屋市中区上前津で+16.2%、1~3位はいずれも名古屋市となっていますが、4位以下には知立市、東海市がランクインしています。
大阪圏の1位は、奈良市西大寺国見町で+9.4%、2位は京都市上京区、3位は大阪府箕面市でした。トップ10のうち、大阪市は6位(城東区中央)と8位(福島区福島)のみで、他には高槻市、堺市など、郊外の街がランクインしています。
さらに、東京圏では1~6位を千葉県流山市が独占、7~10位もすべて千葉県(市川市・柏市)となっています。

2. 東海圏の公示地価ランキング。名古屋市近郊の住宅地の地価が大きく上昇
次に、住宅購入に最も影響がある「住宅地」の地価について詳しく見ていきましょう。
今回は東海圏(静岡・岐阜・愛知)、関西(大阪)の住宅地について解説します。
※公示地価は市区町村ごとの住宅地の公示地価の平均で、㎡あたりの金額(円)です。
※「前年比(%)」は、市区町村ごとの住宅地の平均地価で算出しています。地点ごとの前年比を平均したものではありません。
2-1. 東海圏の上昇エリアは全体の59%。前年の51%から続伸
東海圏エリアを市町村(政令指定都市は区)別に見てみると、前年比で上昇・下落しているエリアは次の通りです。
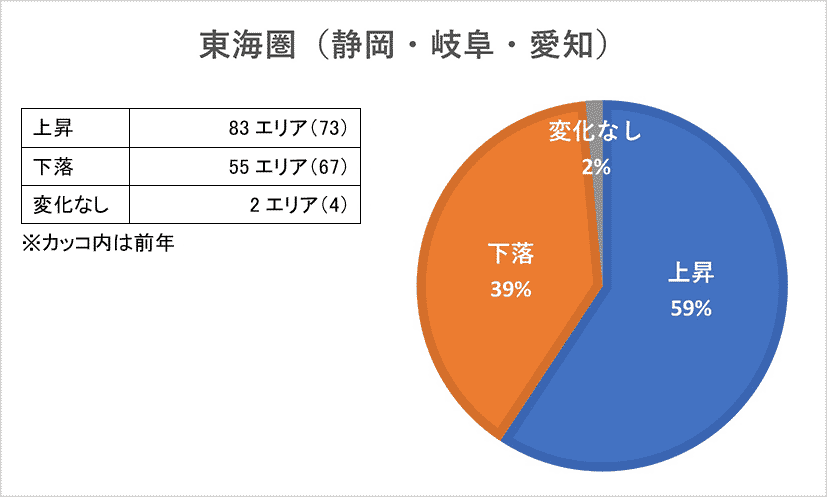
東海圏では、上昇エリアが前年の73エリア(51%)から83エリア(59%)に広がり、全体の約6割が上昇しました。一方、下落エリアは前年の67エリア(46%)から55エリア(39%)へと減少し、上昇エリアが拡大していることがわかります。
2-2. 上昇率トップは2年連続で名古屋市中区。トップ3は名古屋市が独占
それでは、東海圏の上昇エリアと下落エリアのトップ10を見てみましょう。
■2024年公示地価 上昇率・下落率ランキング(東海圏・住宅地)
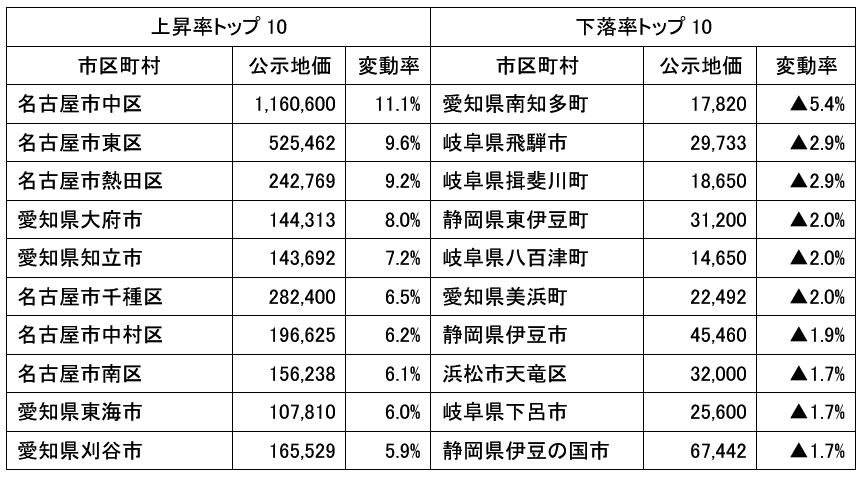
上昇率トップ10はすべて愛知県となっており、1位の名古屋市中区と2位の東区は2年連続。3位の熱田区は昨年の7位から順位を上げています。4~5位の大府市、知立氏は、いずれも名古屋市の南側に位置する郊外の街ですが、名古屋まで電車で15~20分とアクセスがよいベッドタウンで、それぞれ昨年の8~9位から順位を上げています。また、9~10位の東海市、刈谷市も名古屋市の南側に位置する街で、昨年から順位を下げていますが、依然として人気のエリアであることがわかります。
昨年の上昇率と比較してみると、中区は昨年の+11.3%から今年は11.1%に少し下がっているのに対し、近郊の千種区では+2.4%から+6.5%、中村区では+2.6%から6.2%と、上昇の勢いが増しており、需要が都心から郊外に向かいつつあることがわかります。
一方、下落率トップ10の顔ぶれはほとんど変わらず、愛知県の知多半島や、岐阜県の山間部、静岡県の沿岸部などがランキングされています。
2-3. 東海圏の県別地価上昇率トップ5。愛知は上昇が拡大、静岡・岐阜は下落が縮小
さらに、県別に上昇率トップ5をピックアップすると以下のようになります。
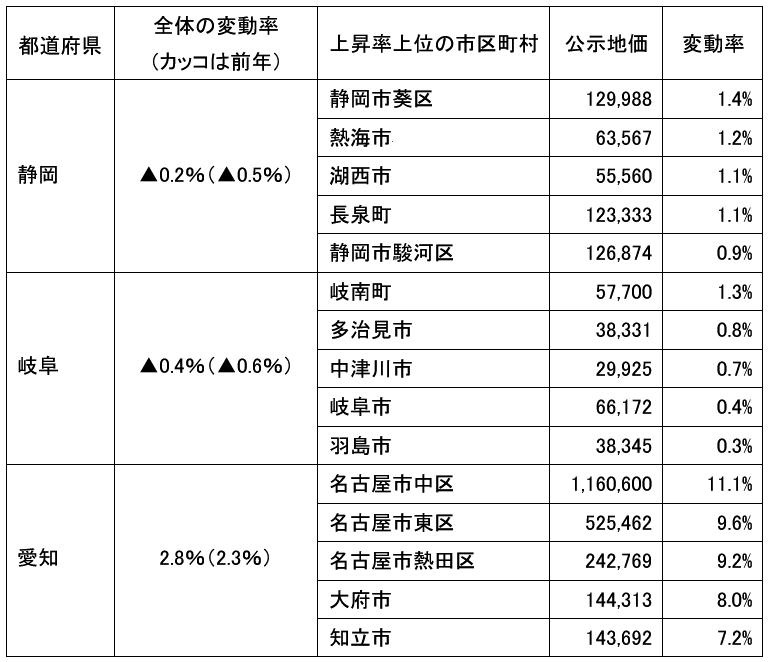
県別に見ると、やはり東海圏は愛知一強で、昨年の+2.3%から+2.8%に上昇を拡大しています。静岡、岐阜は昨年からマイナス幅は縮小したものの、県全体としては下落が続いており、上昇エリアは都心部や一部の観光地に限られています。
静岡県では、静岡市葵区が2年連続のトップで昨年の+1.1%から+1.4%に上げ幅を拡大。2位の熱海市は、観光地としても移住先としても人気が高く、昨年の3位(+0.7%)から順位を上げています。
岐阜県では名古屋へのアクセスがよく、若いファミリー世帯の流入が増えている岐南町が2年連続のトップとなり、上昇率も+1.0%から+1.3%に拡大しています。2位の多治見市と3位の中津川市も、リニア中央新幹線の「岐阜県駅」開業の期待から上昇が続いており、昨年と同順位を維持しています。

3. 関西(大阪府)は、さらに上昇傾向が強まり全体の8割が上昇
次に関西エリア(大阪府)の住宅地の動向を見てみましょう。
3-1. 大阪府の上昇エリアは79%から82%に増加
関西(大阪府)エリアの上昇・下落の割合は以下の通りです。上昇エリアが57エリア(79%)から59エリア(82%)へ増え、上昇エリアが拡大していることがわかります。
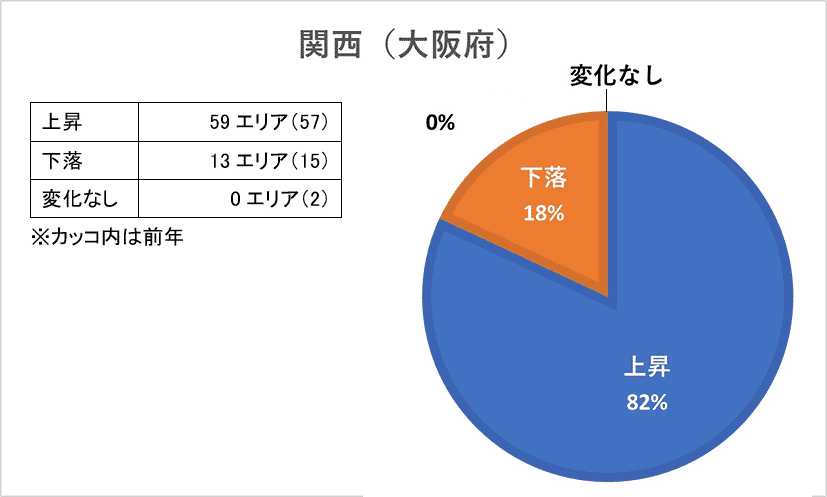
3-2. 関西(大阪府)トップは2年連続で西区。トップ10はすべて大阪市
次に関西エリア(住宅地)の上昇・下落率トップ10を見てみましょう。
■2024年公示地価 上昇率・下落率ランキング(関西・住宅地)
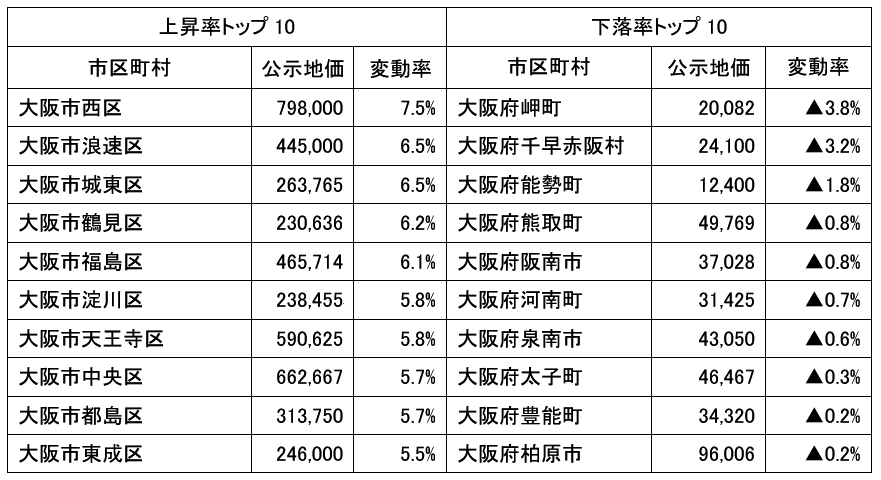
関西(大阪府)の上昇率トップは2年連続の大阪市西区で、上昇率は昨年の+5.5%から+7.5%に拡大しました。またトップ10はすべて大阪市となっており、地価上昇の勢いが増していることがわかります。昨年からの上昇幅が大きい街としては、4位の鶴見区(+1.1% → +6.2%)、3位の城東区(+2.9% → 6.5%)、2位の波速区(+3.2% → +6.5%)などが挙げられ、上昇の波が都心部から近郊エリアに広がりつつあることがうかがえます。
大阪市を除くと13位の守口市がトップで、上昇率は+4.2%。昨年8位だった堺市北区は16位に順位を落とし、上昇率も昨年の+3.1%から+3.5%とそれほど伸びていません。
北摂・京阪エリアからトップ20に入ったのは19位の豊中市だけで、ファミリー世帯に人気の高い吹田市、箕面市、高槻市などはいずれも順位を下げています。
一方、下落率トップ10は前年とほとんど変わらず大阪府の南部と奈良県・兵庫県との県境に近い地域が多くランクインしています。

4. 2024年の公示地価は上昇を加速しつつ近郊エリアに広がりつつある
東海・関西圏の2024年公示地価の動向、いかがでしたでしょうか。
ご覧いただいた通り、地価は3年連続の上昇となり上昇率はさらに拡大しています。最後に、これから住宅購入を検討する方が気をつけたいポイントについて解説します。
4-1. 上昇が近郊エリアに広がりつつある
今年の公示地価の特徴のひとつが、上昇エリアの拡大です。コロナ明けから地価の上昇が続いている中で、上昇の波が都心部から近郊エリアに広がっていることがうかがえます。
東海・関西圏は、首都圏と比べるとまだ都心部の上昇率が高いですが、前年からの上昇幅で見ると、東海エリアでは名古屋市千種区・中村区、大府市・知立市、大阪では鶴見区や城東区など中心部から少し外れた近郊エリアの上昇幅が大きくなっています。 また、2024年に下落(または横ばい)から上昇に転じた街は以下の通りで、都心部からやや距離のある郊外の街が多く含まれます。これから住まいを購入する方は、こうした街に注目してみてもよいかも知れません。
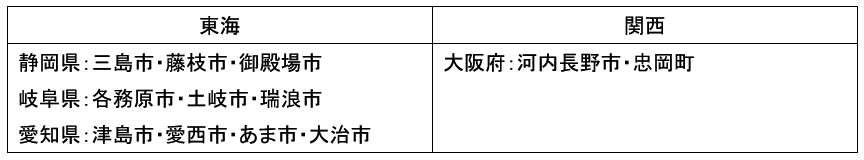
また、今年の大きな関心事だった金利については、3月に日銀がマイナス金利解除を決定し、政策金利を0.0~0.1%に引き上げました。しかし同時に「当面、緩和的な金融環境が続く」と発表されたことで、むしろ金利の先高観は後退しました。5月の住宅ローン金利は、固定金利が若干上昇したものの、変動金利はほとんどの銀行で据え置きとなっており、購入環境としてはしばらくよい状態が続きそうです。
したがって、地価は今後しばらく上昇が続く可能性が高く、さらに郊外へと広がっていくと予想されます。今回上昇率が高かったエリアや、下落から上昇に転じたエリアなどで物件探しを進める場合には、少し早めに動き出した方がよいでしょう。
4-2. 地価はますます「二極化」が進む
もうひとつの特徴は地価の「二極化」が鮮明になっていることです。上昇の波が郊外に広がりつつあるとは言え、各都道府県の上昇エリア・下落エリアの顔ぶれは毎年ほとんど変わっておらず、「上がる街」と「下がる街」ははっきりと分かれています。これは地価の「二極化」と呼ばれ、全国の都市部で起こっている現象です。
つまり上昇が郊外に広がるとは言っても、上昇するのは交通アクセスがよく、商業施設の多い利便性の高いエリアや、再開発が進んでいるエリアなどごく一部ですので、今後ますますエリアの見極めをしっかりおこなうことが重要になってきます。
【関連記事】
住まいの資産価値とは?資産価値の下がりにくい家を買うためのポイント
これから住宅を購入する方は、地域の相場に詳しい不動産会社など、プロのアドバイスを受けながらしっかりエリア選びを進めていきましょう。
本記事のランキングに含まれないエリアの地価や相場情報、資金計画や住宅ローンのご相談は、お近くの住宅情報館までお気軽にお問い合わせください。


.png)